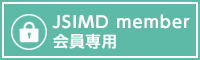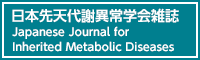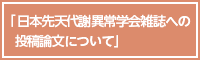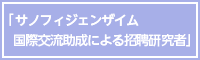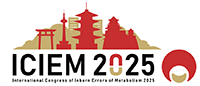沿革と概要
一般社団法人 日本先天代謝異常学会は、1965年に「小児代謝研究会」として発足し、1984年に「日本先天代謝異常学会」と改称、2021年に一般社団法人となりました。発足以来、先天代謝異常症における診療・研究の向上と進歩を目的に活動を展開し、分子生物学や遺伝学の発展とともに、学術・臨床の両面で先駆的な役割を担ってきました。歴代理事長には北川照男、多田啓也、衛藤義勝、遠藤文夫、井田博幸、深尾敏幸、奥山虎之の各氏が就任し、2022年11月より中村公俊(熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座教授)が理事長を務めています。会員数は約700名であり、医師、研究者に加え、看護師、栄養士、心理士、患者家族会など多職種が参画しています。
学術活動
学術集会を年1回開催し、研究成果や臨床経験を広く共有する場を提供しています。また国際的な交流にも積極的であり、2025年には国立京都国際会館において国際先天代謝異常学会(ICIEM 2025、大会長:中村公俊)を開催し、国際連携強化と若手研究者の育成に努めています。
教育活動
教育分野では、2005年より毎夏「日本先天代謝異常学会セミナー」を継続開催し、一般小児科医や研修医に向けて基礎知識の普及を図っています。さらに、アドバンスセミナーも実施しており、専門性の高い教育の機会を提供しています。
臨床と社会的役割
本学会は、希少難病である先天代謝異常症に対して、診断・治療ガイドラインの作成、患者登録制度の整備、特殊治療薬や特殊ミルクの供給体制の確保、ドラッグ・デバイスラグの解消、新規診断法や治療法の開発に積極的に取り組んでいます。また、保険診療システム、小児慢性特定疾病や指定難病制度の課題への対応、行政への提言などを通じて、医療制度の改善にも貢献しています。